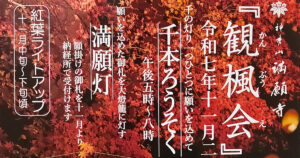竹山流の津軽三味線奏者は全国各地におられて、それぞれが想いをもって演奏活動をされています。その中でも「高橋」の名字をもつ人がいます。
今回は竹山流 津軽三味線における高橋の名字について、名取の制度、初代 高橋竹山の芸名の由来などを紹介しながら、私が知っていることを書いていきます。
竹山流 津軽三味線で「高橋」になるまでのステップ
竹山流 津軽三味線の流派では、いきなり「あなたは才能があります。では高橋名字をあげましょう」とはなりません。何事にも順序というものがあり、まずは「名取」をする必要があります。
名取制度で芸名を授かる
日本の伝統芸能の世界では、芸名をつけるとき、師匠から1~2文字をいただいて芸名とする、流派の名字を継承する、何代目(有名な芸名)を襲名する、家元の名前を引き継ぐ、といったパターンがあります。
一般的に芸名をいただくことを「名取」と呼び、名取になって、初めて流派の正式な弟子として認められます。名取をしていない段階はあくまで「生徒」であり、先生と生徒の関係。名取をしてようやく師匠と弟子の関係となり、深い信頼関係が生まれるのです。
名取をするためには、一般的に「名取料」といわれる費用が発生します。私は津軽三味線を始める前、お稽古に通って演奏技術が上手になり、一定のレベルに達すれば、無料で芸名がもらえると思っていましたが、世の中、そう甘くはないようで・・・。家元制度や流派が存在するということは、そういうことなのです。
さまざまな三味線奏者に話を聞いたところ、流派によって名取料の考え方(金額)が変わってくるため、何とも申し上げられませんが、それなりのまとまったお金が必要になります。気になった方は「名取料」「名取 費用」などで検索してみてください。
私が所属している竹山流 津軽三味線の会では、名取料だけと聞いています。三味線の流派や所属する会によっては、名取試験の受験料、お師匠さんや家元への御礼、お名札代(木札)、名取のお披露目会の費用(舞台の施設料・設営費・食事代・お土産代・お車代なども含む)、流派の紋が入った着物代、新しい三味線の購入など、そのほか諸々の出費がかかるケースもありますので、詳しくはお師匠さんに聞いてみてください。
こういうことを書くと「家元制度は悪なのではないか?」と思われがちですが、名取料は流派を保つための運営資金として活用されますし、昭和の民謡ブームが去った今、家元も正直そこまで儲かっていません。むしろ若手が減り、業界としては縮小傾向にあるくらいです。
家元制度は、伝統芸能における流派の運営と芸の伝承を行うための仕組みで、家元制度によって芸が次の世代に継承され、伝統が守られてきました。この制度により、流派の技術や文化が途切れることなく今に伝えられています。
名取をするということは、流派の暖簾(肩書き・看板)を分けてもらうわけですから、そういった費用として納得できる方が名取をして、いただいた芸名を名乗り、「●●流の奏者」として活動することが許されるわけです。
ちなみに、私の場合はお師匠さんが「高橋栄水」先生という芸名ですから、師匠から「水」の文字をいただいて、「水山」となりました。正規の手順を踏んで名取をしたため、「竹山流 津軽三味線奏者の水山です」と自己紹介で名乗ることができます。
高橋竹山の芸名の由来
初代 高橋竹山の本名は高橋定蔵で、「竹山」の芸名は成田雲竹が名付けたと言われています。
成田雲竹は津軽民謡の父と呼ばれた民謡界のレジェンド。日本民謡協会から名人位を授かり、誰もが敬う存在でした。そんな成田雲竹が唄の伴奏者として当時はまだ無名だった高橋竹山を指名し、名コンビとして一世を風靡するわけですが、その成田雲竹が本名で活動していた高橋定蔵に、自分の名前から「竹」の文字を与えて芸名が「竹山」になりました。
二代目 高橋竹山氏の公式X(旧Twitter)の投稿に、高橋竹山の芸名の由来が書かれていました。
成田雲竹先生の「竹」と、「山」の部分は『「竹の山」は根が張って動かなくて良いと言うことで「竹山」になりました』とのこと。
青森県の津軽地方には雄大な岩木山があり、かつて高橋竹山は「山が大好きでありました」とインタビュー映像で語っていたため、「山」の文字になったのも何かのご縁と言えるかもしれませんね。
「高橋」名字について
「高橋」名字という称号は、初代 高橋竹山(高橋定蔵)の名字である「高橋」から来ています。
竹山流の津軽三味線の場合、前途のとおり、まずは名取をして芸名をもらいます。そして最初は「本名の姓+芸名」もしくは「芸名のみ」で活動をする方が多いようです。
その後、「高橋」名字になるステップとしては、所属する会にもよりますが、
- 名取 → 高橋(師範)
- 名取 → 準師範 → 師範 → 高橋(師範)
このような段階を経て、「高橋」名字になるケースがほとんどです。
各ステップごとに費用が発生しますので、どこまで取得するかは個人の判断に委ねられています。とはいえ、費用を納めれば誰でもなれるわけでもなく、流派の資格・称号ですから、ある一定のレベルを超えた方など、それぞれの師匠や家元の基準によって昇格の可否が決められるようです。
教室を構えて誰かに教えるなら「準師範」以上、弟子に名前(芸名)を出すなら「師範」以上、高橋名字で活動したいなら「高橋」を取得するようなイメージというか、暗黙のルールのようなものが存在します。
「高橋」名字の称号を得ても、師範であることは変わらないため、「本名の姓+芸名」もしくは「芸名のみ」で活動を続けられる方や、芸名を使わずに「本名」で活動していくと決めた方は、お師匠さんに認められたうえで、「高橋」名字を取得されないケースもあります。
日々の精進が大切
一番大切なことは、名取をする/しない、「高橋」名字を取得する/しないにかかわらず、日々のお稽古を積み重ねて、常に自分の技量を高めていくという意識を持つことです。
最近は少なくなりましたが、かつて伝統芸能の業界において、お師匠さんや家元から芸名(もしくは高い地位など)をもらってあぐらをかき、現状に満足して努力を怠る人がいたそうです。それでも多くの人々は「芸の質」ではなく、「肩書き」で判断する傾向があり、芸をすれば称賛されるため、本人にとっても気づきにくい境遇に置かれ、そこで満足してしまい、本業の芸ではない別の享楽にふけって、そのまま時が過ぎ去っていくケースもあったとか。
そのようにならないよう、常に謙虚な姿勢であること。自分を客観視できるようにしたいものです。
名前(芸名)をいただいたのなら、それに見合った芸を披露して、芸名を授けてくれたお師匠さんに恥をかかせないように精進する。そして、ますますお稽古に励み、舞台で芸を披露していく中で、さらに芸人として成長し、深みを増した演奏ができるようになっていくのが理想的ではないでしょうか。
初代 高橋竹山からつながる芸の心と、竹山流の弾き三味線の音色を継承する。そういった覚悟がある方は、ぜひ名取をして、ゆくゆくは師範や高橋を目指してみてください。