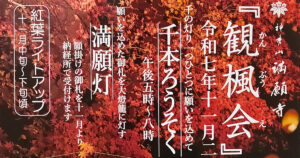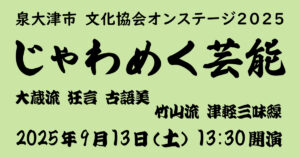2025年10月12日(日)に奈良市で開催された「第10回 春日野音楽祭」のまちなかステージに出演しました。御蓋山と氷室神社への奉納演奏として行ったライブ当日の様子をレポートしていきます。
JR奈良駅から、まちなかステージの舞台「氷室神社」に向かう
電車にゆられてJR奈良駅に到着! まちなかステージの会場のひとつである「氷室神社」へは近鉄奈良駅からの方が近いのですが、今回はJR奈良駅から向かいます。

駅の構内には、おなじみとなった奈良県の公式マスコットキャラクター「せんとくん」がお出迎え。このウェルカムボードで記念撮影をされている外国人観光客の方もいました。
改札を出ると、真正面に奈良市観光案内図があります。

「この地図を見てね」と言わんばかりの迫力! 左上に赤背景の白文字で「i」(information)と大きく書かれたピクトグラムが目を引きます。普段はスルーするのですが、今日はどんなもんかと見てみることに。

じっくり地図を見たところ、東大寺や春日大社はもちろん、興福寺、元興寺の位置もわかりやすくマークされていました。拡大写真には写っていませんが、奈良駅の西側には平城宮跡、唐招提寺、薬師寺の場所も目立つように記されています。
バス路線図のチラシ(ルートマップ)も配布されているため、初めて奈良を訪れた観光客の人にとても役立ちそう。さらに、東口のエスカレーターを降りたところに奈良市総合観光案内所があるので、そこに立ち寄るとなお良しですね。
今回の目的地である氷室神社は、奈良県庁の先、奈良国立博物館の前あたり。JR奈良駅からだと、徒歩20~30分くらいでしょうか。ちょっと時間に余裕があるため、駅ビルにあるスーパーマーケット(KOHYO JR奈良店)で買い物をして、歩いていきます。

春日野音楽祭の会場となるエリアには、このようなフラッグが立てられていました。早朝、もしくは前日からスタッフの方々が準備をしてきたのだなと感じさせられます。
奈良時代に創建、平安時代に移転された由緒ある氷室神社
ならまち~奈良公園エリアを歩いて、氷室神社に到着。

氷室神社は奈良時代(710年頃)に創建された由緒ある神社で、氷の神がお祀りされています。もとは春日山にありましたが、平安時代(860年頃)に現在の地に移転したのだとか。当時は冷凍庫がありませんから、氷は大変貴重なものでした。冬にできた氷を「氷室」と呼ばれる場所に保管して、暑い季節に天皇・皇族・貴族に献上していたようです。エアコンのない時代、上流階級や権力者の人たちは、この氷で涼をとり、夏を快適に過ごしていたと考えられています。
そんな歴史があり、現在では製氷業者をはじめ、氷・冷却・冷蔵に関する事業を営む企業などが繁栄祈願に訪れるほか、氷の神を祀る神社として多くの人々に親しまれています。氷の上におみくじを乗せると文字が浮かび上がる「氷みくじ」、夏季限定で行われている「かき氷献氷」、御朱印も人気みたいです。
開演前にご祈祷あり
開演前には、氷室神社の神職と春日野音楽祭のスタッフの方々、最初の出演者が集まってご祈祷をされました。私もその様子を後ろから見守りました。
その後、定刻どおり10時から演奏がスタート。まちなかステージ【氷室神社】のトップバッターはHopinsongsさん。透き通る歌声と柔らかな楽器のサウンドが境内に響き渡り、会場が温かな空気に包まれました。
続いて、水山も演奏の準備を進めます。

氷室神社のステージでは、このように演者が本殿に正対して演奏するのが特徴です。奉納演奏の名の通り、神様に向かって演奏を行います。(観客の皆様は左右や後ろ側にいらっしゃいます)

竹山流 津軽三味線の音色を響かせられるように。
演奏を開始する前は、本殿に向かって二礼二拍手一礼。それから約25分ほど奉納演奏をさせていただきました。

雨の心配や情報の行き違いもあり、簡易な服装での演奏となりましたが、今の自分にできる精一杯で演奏しました。
演奏した曲
- 黒石よされ
- 新じょんから節
- 三味線じょんから
- 三味線よされ
- 曲弾き
演奏中は目を閉じて静かに集中し、竹山流 津軽三味線の音色をしっかりと響かせられるよう努めました。野外でのライブが初めてだったこともあり、湿度の影響、棹の滑り具合が思うようにいかない、参拝者によって突然背後で本坪鈴(ガラガラ)が大音量で鳴らされるハプニングなど、いろいろありつつ、良かった点、反省点、すべてが貴重な経験となりました。この経験を今後の芸の糧として活かしていきたいと思います。

氷室神社の神職の皆様をはじめ、春日野音楽祭のスタッフの皆様、音響スタッフの皆様、お越しくださった皆様、本当にありがとうございました。
春日野音楽祭を振り返って
奈良県の音楽祭に参加するのは初めてで、ワクワク感と緊張が同じくらいあって、どうなるか自分でも予想できませんでしたが、音楽を通じて人との出会いや交流が生まれることの素晴らしさを、あらためて感じました。
春日野音楽祭のように、ライブ会場が複数ある野外フェスでは、すべてのミュージシャンの演奏を聴くことがかないません。会場間を移動する時間もかかるため、その時、その場にいた人だけが生のライブステージを堪能できる。本当に一期一会であり、瞬間瞬間に生まれては消えていく音のひとつひとつが、通りかかった誰かの心に届くかどうか。音楽にはそういった儚さのある芸術という側面がある。
印象的だったのは、氷室神社のステージでの全員合唱。誰もが知るような名曲をみんなで歌う。この一体感こそが音楽の力なのだということ。みんなの想いや気持ちが歌声にのって、ずっと遠くまで届きそうなくらい力強く、それと同時になんともいえない清々しさと爽快感がありました。メロディ、リズム、ハーモニーが組み合わさって音に厚みが生まれ、隣にいる人に笑顔が伝搬していく。そんな人間の優しさが感じられるひとときだったように思います。
演者もスタッフも、それぞれが春日野音楽祭の当日に向けて、最高のステージになるよう準備を重ねてきた。参加した人たちがイベントを楽しみ、成功させようと努力した。ある人は誰かを楽しませようと工夫した。それだけで尊く、美しい。私もそういった姿を見習って、間違わないように、見失わないように、励んでいきたいものです。